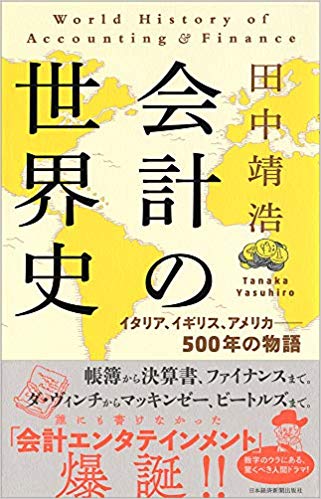前回の記事では会計の歴史について、田中靖浩氏の「会計の世界史」を元にイタリアの大航海時代からイギリスの産業革命まで概観しました。
【書評】『会計の世界史 イタリア、イギリス、アメリカ――500年の物語』は一冊で会計と簿記が身につく良書。簿記初心者でも読めてオススメ。
今回は1920年代以降のアメリカとグローバル化する会計について、現代に寄せて見ていきたいと思います。
アメリカの時代ー現代に通じる会計の理論の登場
イギリスが産業革命を迎える中で、アメリカも徐々に発展への原型を整えていきます。ジャガイモ飢饉で飢えたアイルランドの人々がアメリカへ移住したり、イギリスやヨーロッパの投資マネーがアメリカの鉄道会社に流れたりするようになります。
なおこの際には破産処理に加えて「監査」というビジネスを始めた会計士が活躍するようになりますし、これが現在のデロイト・PwC・KPMGと言った会計事務所に繋がっていきます。またアメリカの鉄道は自己資本比率が低く常に倒産の危険があるために投資家は決算書を読み出します。これが「経営分析」の始まりです。
1920年代には世界恐慌が起こりました。この際にルーズベルト大統領はSEC初代長官にケネディ大統領の父・ジョーを指名、景気回復策として預金と投資の分離を定めた「グラス・スティーガル法」と「証券法・証券取引法」を制定します。同時に会計分野においても公開企業の会計制度の基礎が完成します。具体的には①決算書をちゃんと作らせて②決算書をちゃんと作っているか監査してもらい③将来的に株を買う見込み客までもを保護する趣旨でディスクロージャー制度を設けました。
これらの実施には大変な労力がかかりましたが、裏で支えていたのがSEC初代長官となったジョーでした。
一方で公開会社には社会的責任が大きくのしかかることになり、私的利益誘導に該当するインサイダーは厳しく禁じられ内部監査も重要視されるようになりました。
そしてこれらを一連のルールにしたのがU.S.GAAPと呼ばれる米国における会計基準です。それぞれの会社の会計基準が異なっては困るため、一つのルールに皆が従うことで公平な会計を目指したのでした。
グローバル化する会計
さて、20世紀には産業革命から始まる工業化に加えて「情報化」も進みます。有線だった通信が無線になり、レーダーになり、この情報化と「工業化」を加えて20世紀が「グローバル化」していきます。
この辺りは戦争ともかなり関連があるので、興味ある方は原著「会計の世界史」を読んでみると良いと思います。イギリスとドイツの攻防が叙情的に描かれていてとても面白いです。
英米の会計、グローバル化する世界と時価主義へのシフト
さて世界のグローバル化が進む中で、会計基準についても国際化すべきであるとの議論が登場します。しかしこれはいまだ解決されない課題であり、英米の二国のどちらがイニシアチブをとるかを巡って、今なおはっきりとした答えは出ていません。
しかし英米の二国が会計をリードする中で資産評価にも変化が訪れます。これが「時価主義へのシフト」です。
従来会計は取引をする自分たちにとって儲けを適切に分配するための手段として商人が実施するものでしたが、500年の会計の歴史の中で徐々に会社が大きくなり外部株主からの資金を調達することで、株主や投資家といった他人のためのものへと目的がシフトしてきました。
そうなると資産評価の方法も利害調整を目的とする「原価主義」から投資家への正確な情報の提供を目標とする「時価主義」へとシフトしていきます。今でも日本やドイツといったものづくりの得意な国では原価主義を採用する傾向にあるものの、時価主義を採用する英米の影響力の強い現在、ますます時価主義がグローバルスタンダードになっていくだろう、というのが『会計の世界史』での著者田中氏の主張でした。
1999年に米国はダラス・スティーガル法を撤廃し、結果あらゆる業務を行う巨大金融機関が登場するようになります。ファンドも登場し、金融に産業シフトが起こります。
この中でキャッシュ回帰の流れが強まり、決算書もB/S、P/Lに加えC/S(キャッシュ・フロー計算書)の三本柱となっていきます。
19世紀には連結決算も始まりました。前回の記事で述べたように鉄道会社が19世紀には多く登場したわけですが、一部の鉄道会社は経営不振に陥った競合鉄道会社を買収していきます。となると決算書も繋ぐ必要が出てきます。これが文字通り「連結決算」の始まりでした。
これに加えて鉄道会社は広いエリアを「管区」に分割し、経営を行なっていました。このような管区に分割したセグメント管理によって製造業においても同質的大量生産が可能になります。
この際、製品の原価を計算するために「管理会計」という概念が登場します。外部への報告という守りの会計「財務会計」に加え、会社の内部で利用するための攻めの会計「管理会計」の二本立てが会計の基本になっていきました。
デュポンと投資利益率(ROI)
19世紀の企業経営は規模拡大を重視しており、企業買収ももっぱら競合を潰す目的でなされましたが、20世紀前半には効率を重視し、コスト削減を目指す経営へとシフトし、企業買収もコスト削減を目的とするものが増加しました。その典型例がGEになります。
この際に難しいとされていた各製品や事業ごとのハードル設定の示唆を見出したのがデュポン式経営です。
デュポンは自己資本が多い経営であり、ROI(投資利益率)=P(利益率)×T(回転率)の指標の元に投資に見合った利益を出すことを重視した経営を実施しました。
20世紀後半。ファイナンスの登場
しかし、過去のコストが算出しやすいばかりにこればかりに注目し、本来重要であるはずの未来に得られるリターンが算出しづらいという理由から軽視されるのは特に情報・金融・サービス業にとっては致命的です。
そこでこのような業種を始め、決算書には出てこない「隠れ資産」を持つ会社の価値を増やすために登場したのが「ファイナンス(corporate finance)」の概念です。
企業価値の算定は①会社を買収した後のキャッシュフローを見積もり、②それを現在かちに割引計算することで求められますが、これらにより算定された企業価値はファイナンス思考を持つ経営者、ファンドや金融機関の力を借りながら増加させることができます。
21世紀の現在、会計ではこのファイナンスの思考がますます重要視されてきています。
まとめると、会計の歴史は従来イタリア・オランダで実施されていたように「商人が自分たちのために帳簿をつける」すなわち「簿記」から始まりました。その後決算書を読み、投資する投資家や株主といった「他人のために」実施する「財務会計」がイギリス・アメリカで始まり、そしてアメリカとグローバル時代において再び管理会計とファイナンスが「自分たちの経営のために」行われる会計として登場しました。
「会計の世界史」ではこのような世界史の流れにしたがって会計の全体図が読めば読むほど頭に入ってきました。特に後半ではビートルズとマイケルジャクソンのエピソードを導入として会計を記述するシーンがあったり、マッキンゼーやペプシといった誰もがしる企業のエピソードもあり、非常に面白いです。まだお読みで無い方はぜひ。過去読んだ会計・簿記の本で一番面白く、ストレスを感じずに読めます。